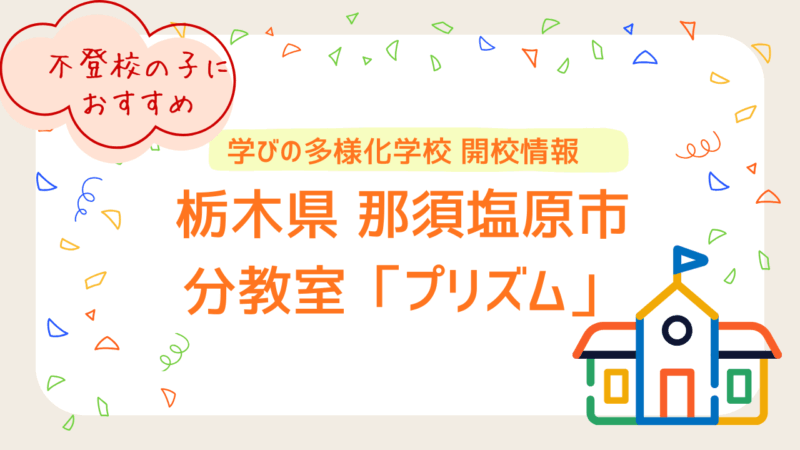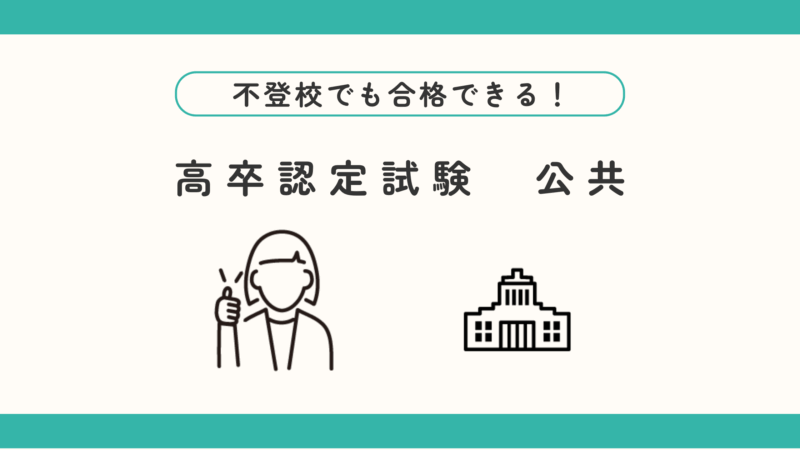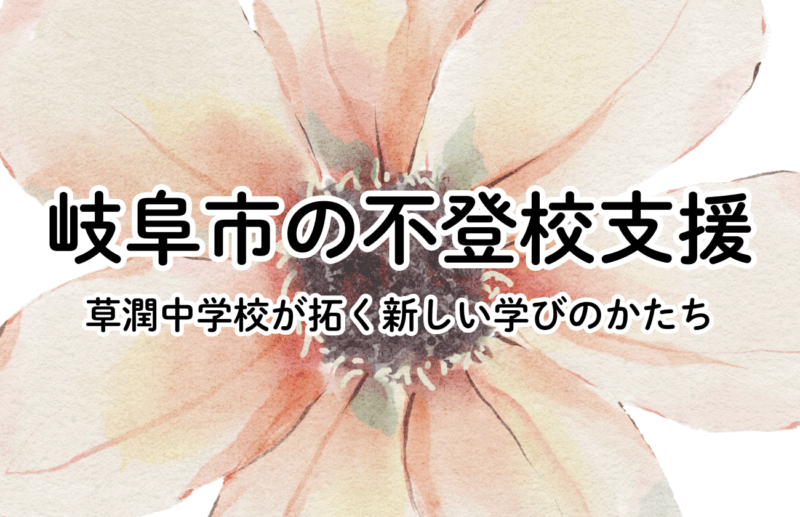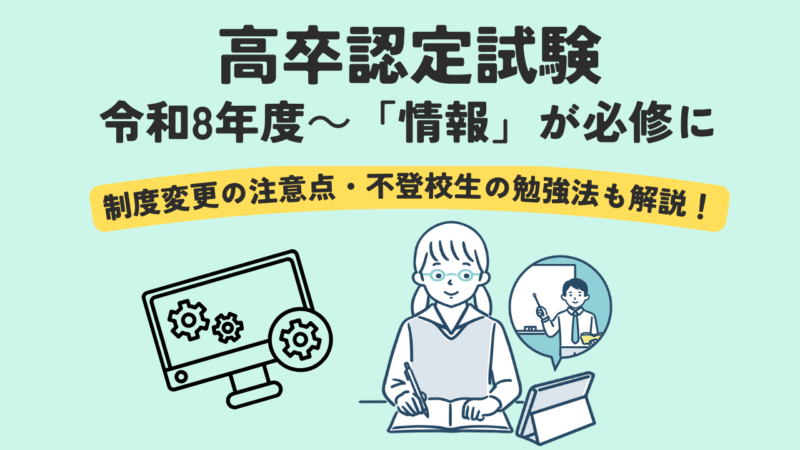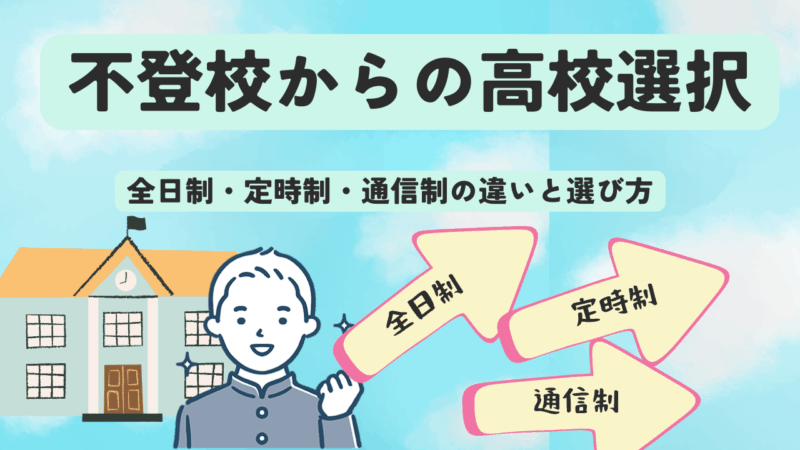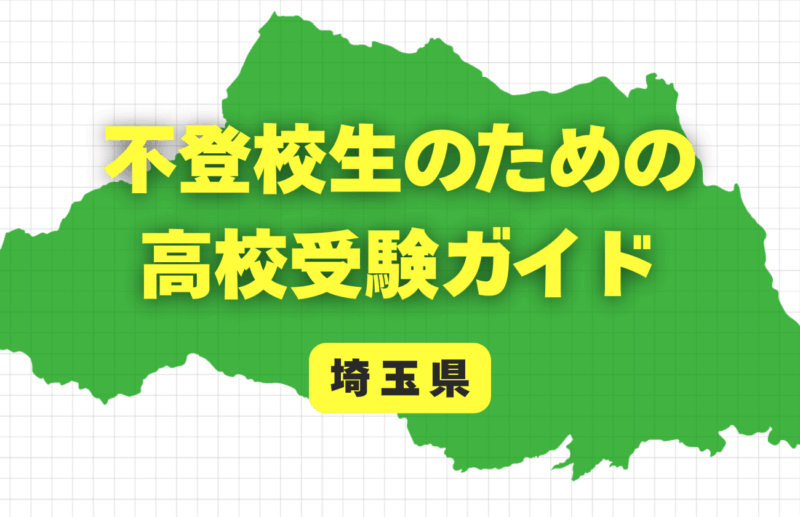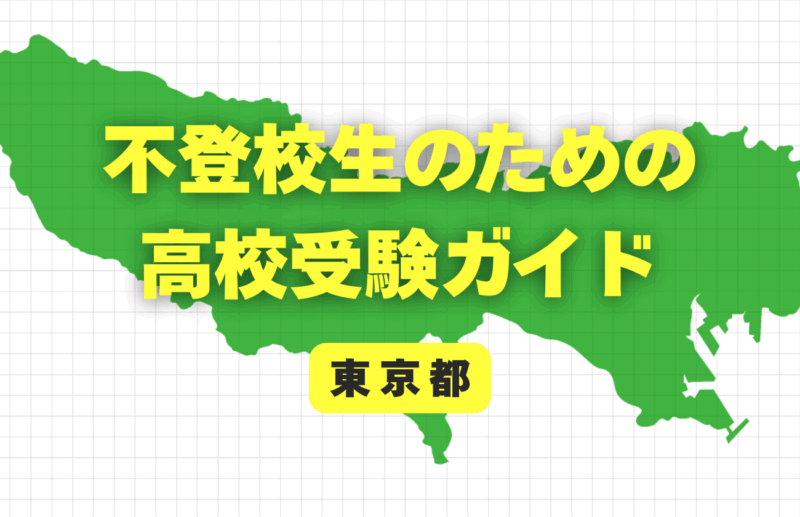不登校の学びは成績に反映可|出席扱い・評価の条件【2024年文科省通知対応】
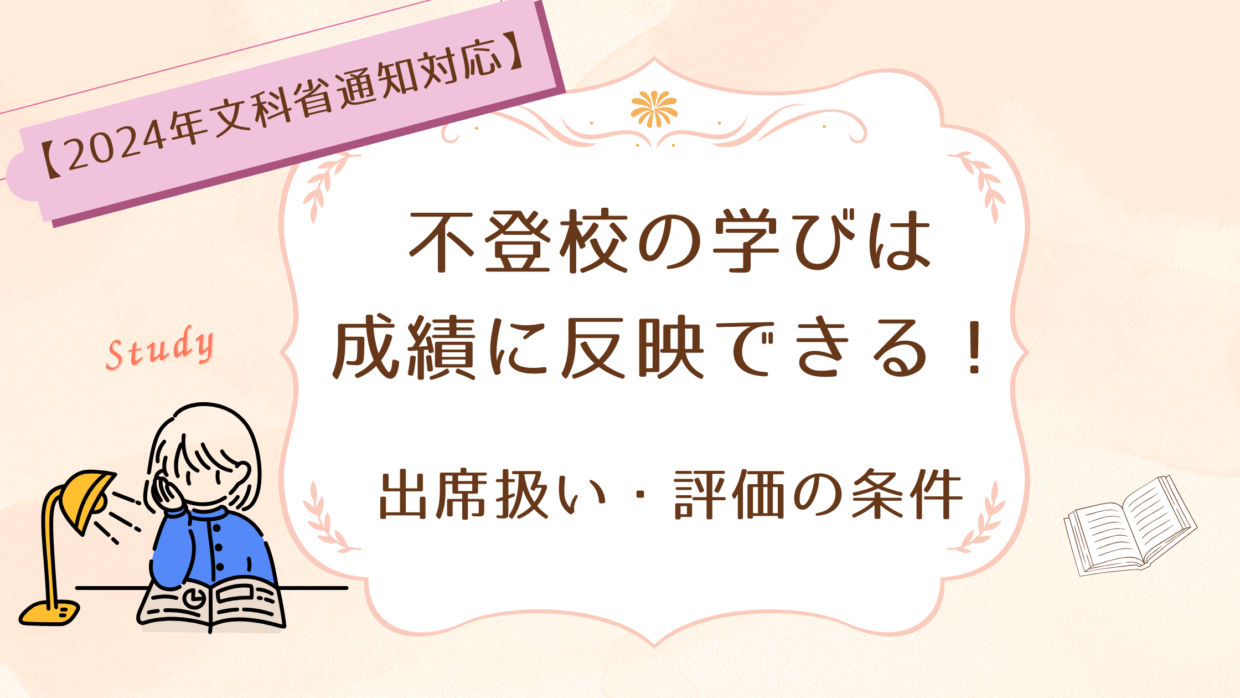
「家で頑張って勉強しても、評価してもらえないのでは…」
「学校で勉強しないと進学に不利になってしまう?」
こうした不安を抱える保護者の方は少なくありません。まずお伝えしたいのは、
不登校の期間に取り組んだ学びは、条件を満たせば学校の成績や出席扱いに反映できるということです。
文部科学省は、学校外や家庭での学びを柔軟に評価する仕組みを整えています(令和6年〈2024年〉の法令改正・通知により明確化)。
この記事では、制度の要点と、保護者の方が実際に動き出すための道筋をやさしく整理します。
まず知っておいてほしい3つのポイント
- 学校外の学びも評価の対象になる
- 学校で評価してもらうために:学校側が確認できる根拠と、定期的な連携が必要
- すべての教科で無理に評定をつける必要はない(所見欄で学びを記述して残す方法あり)
評価対象になる学び
不登校状態でも、評価の対象になり得る学びの場には、教育支援センター(適応指導教室)、フリースクール、オンライン学習、家庭学習、個別指導など多岐にわたります。
評価対象になりやすい例
- 支援センター・フリースクールでの学び(報告書・出席証明がある)
- オンライン教材や学校配信の課題への取組(受講履歴・提出物が残る)
- 家庭学習(教科書・ワーク・レポート・作品づくり等を記録している)
大切なのは、在籍校の教育課程(教科・単元など)に照らして妥当な内容であること、学校が学習のようすを定期的・継続的に把握できていること、そして学校と本人の関わりが保たれていることです。これらの条件が揃えば、登校できていない期間の学びでも出席扱いや成績反映の対象になり得ます。
出席扱い制度の活用例は、こちらも参考にしてください。
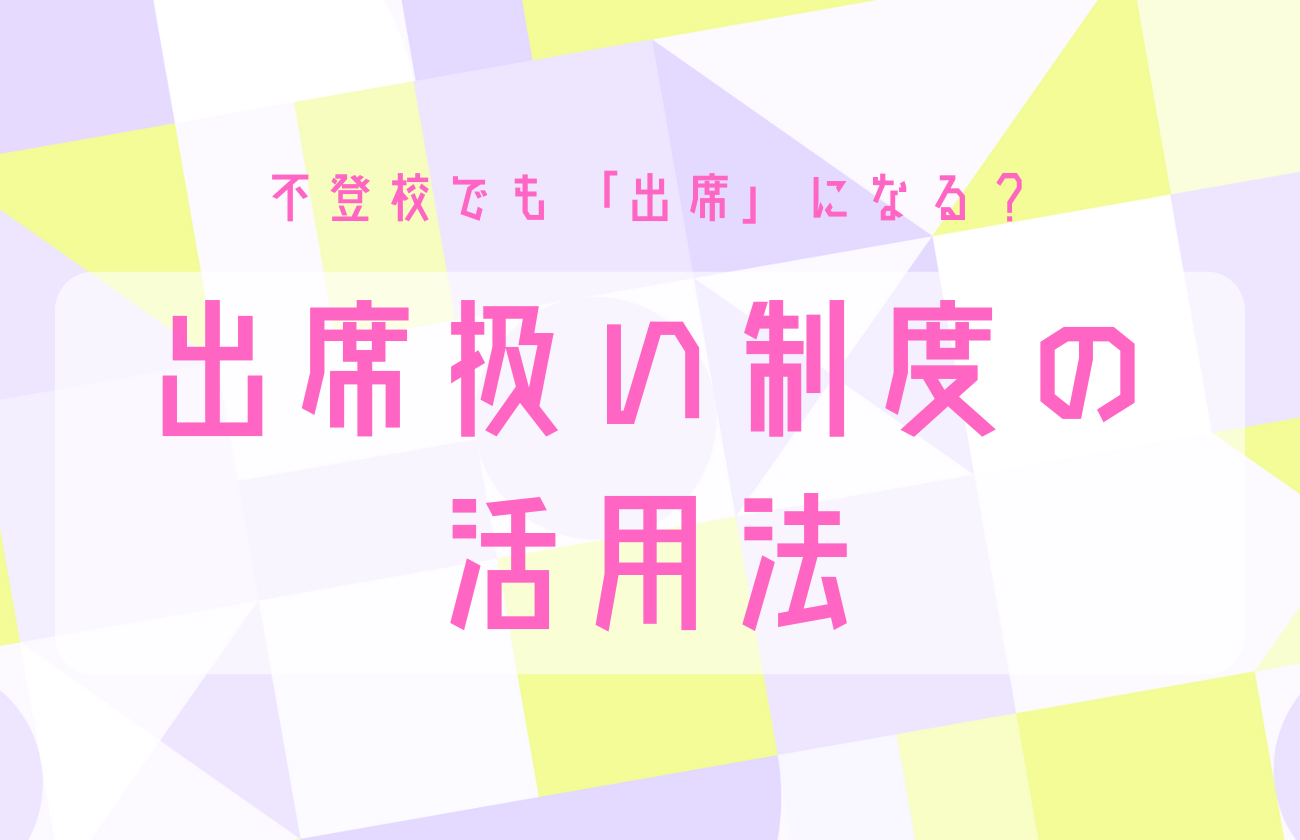
学校側が確認できる根拠・定期的な連携
不登校でも、学習をしていればそれが必ず学校の評価となるわけではありません。
学校の評価として認められるには、「がんばったこと」を証拠として見える形にすることと、
無理のないペースで学校とつながり続けることが大切です。
注意したいポイントとしては、具体的な運用・判断は自治体や学校によって異なります。
学校外の学習について、出席扱いや成績反映を検討する場合は、まずは所属している学校や自治体の教育相談窓口へ相談してみるのがよいでしょう。
「欠席中の学習について、学校の教育課程に沿う形で評価いただける方法を相談したいです。
学習ログと提出物の整理、定期的な共有も続けます。必要な様式や頻度を教えてください。」
また、出席扱いや成績反映とならなくても、進学や就職の選択肢がなくなるわけではありません。
詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。
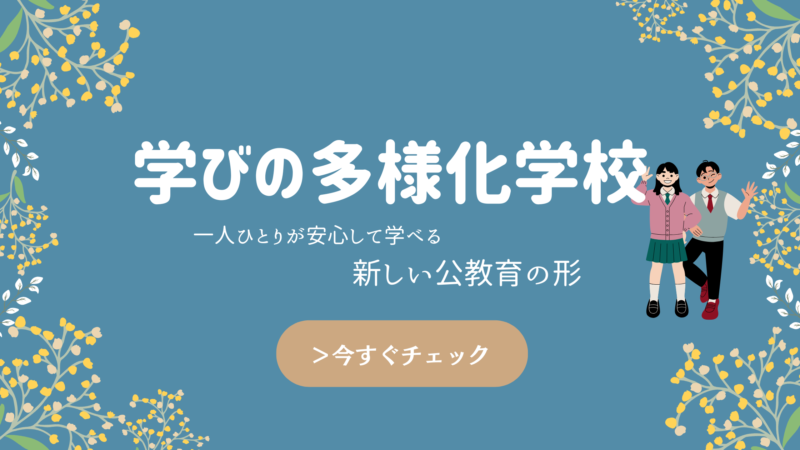
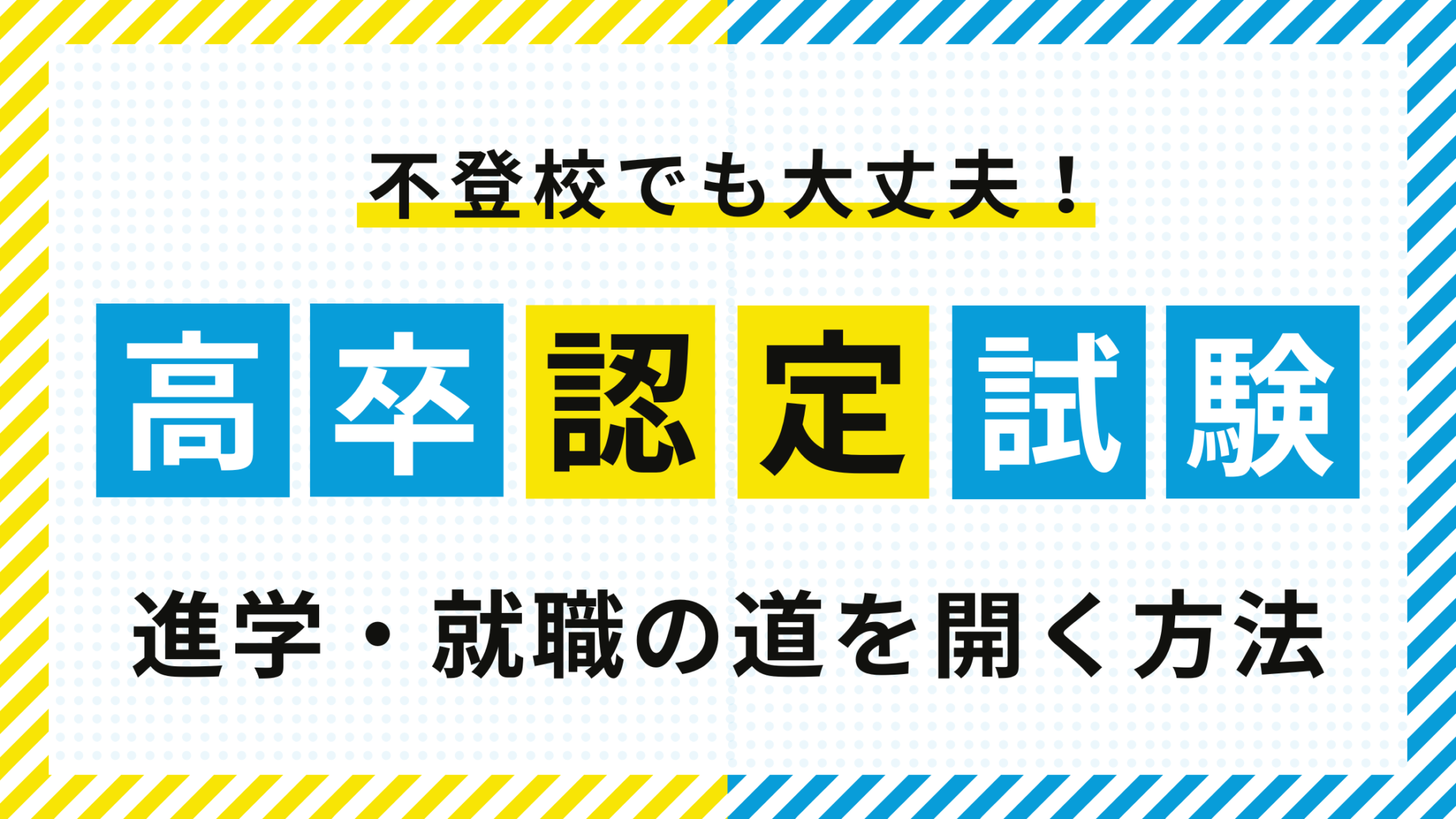
根拠が集めづらい教科はどうしたらいい?
根拠が十分に集めづらい教科まで無理に評定をつける必要はありません。国の通知では、
指導要録や通知表の「所見欄」に学びの状況と成果を記述して残す取り扱いも示されています。
評定が難しい場合でも、努力や到達の手がかりを文章で丁寧に残すことで、次の学期・学年につながる情報になります。
- 代替の示し方:「〇〇教材で△△単元に取り組み、□□ができるようになった」「作品制作で表現意欲が高まった」など、具体的に。
- 実技・技能系:家庭での工夫(動画・写真・制作過程メモ)を添えると、先生が様子を把握しやすくなります。
よくある質問
- Q. どの学習でも必ず出席扱い・成績反映になりますか?
- A. 学校の裁量です。国が示す要件(妥当性・定期的把握・学校との関わり)が満たされ、根拠が整っていることが前提になります。
- Q. 全教科に評定を付ける必要はありますか?
- A. 必須ではありません。根拠が十分でない教科は、指導要録の所見欄に学びを記述する方法も通知で示されています。
- Q. 対象はどの学年ですか?高校生は?
- A. 今回の明確化は義務教育段階が中心です。高校段階には別の仕組み(通信教育による単位認定等)があるため、在籍校にご相談ください。
困ったときは、ひとりで抱え込まないで
記録や連携を続けるのは、保護者にも負担がかかります。REOでは、学習計画づくりや学校とのやり取りの整理をお手伝いしています。
学校との連携に限らず、不登校のお子さまの状況についてもご相談いただけます。
お気軽に下記のお問い合わせフォームや公式LINEよりご連絡ください。