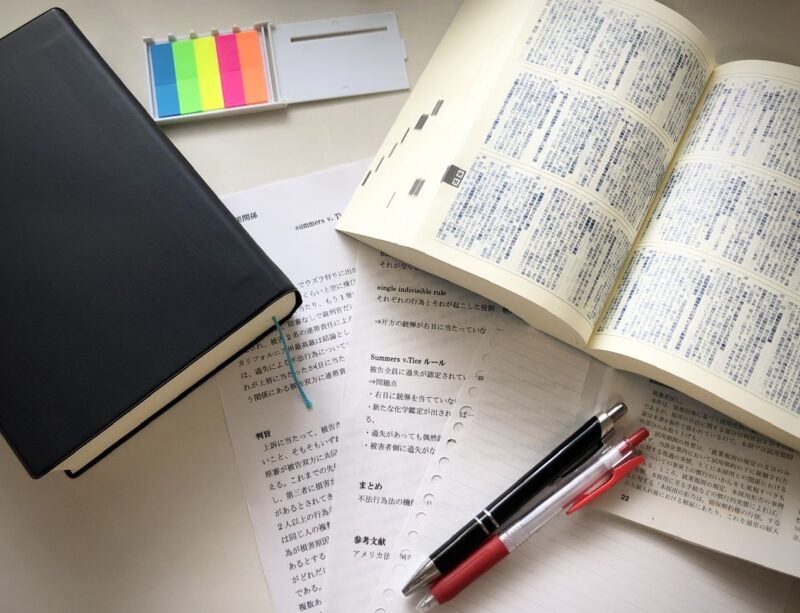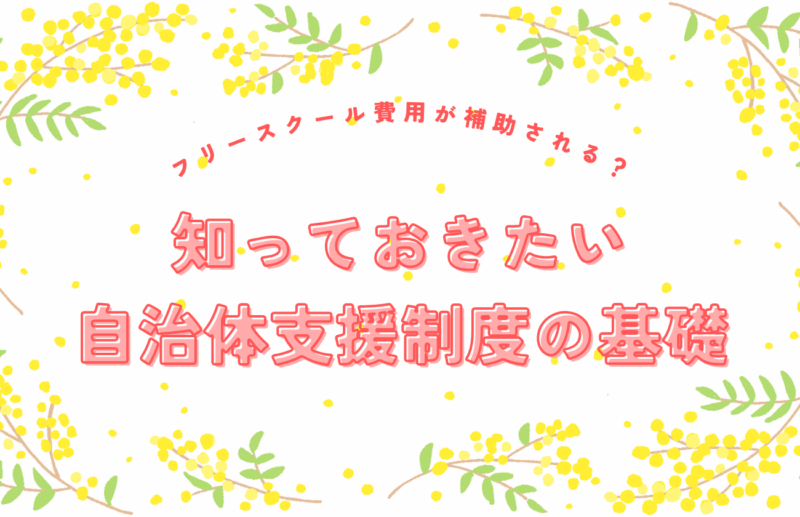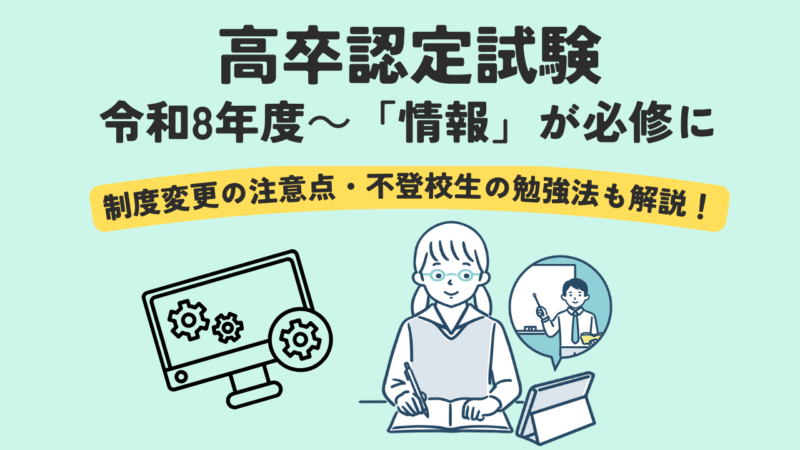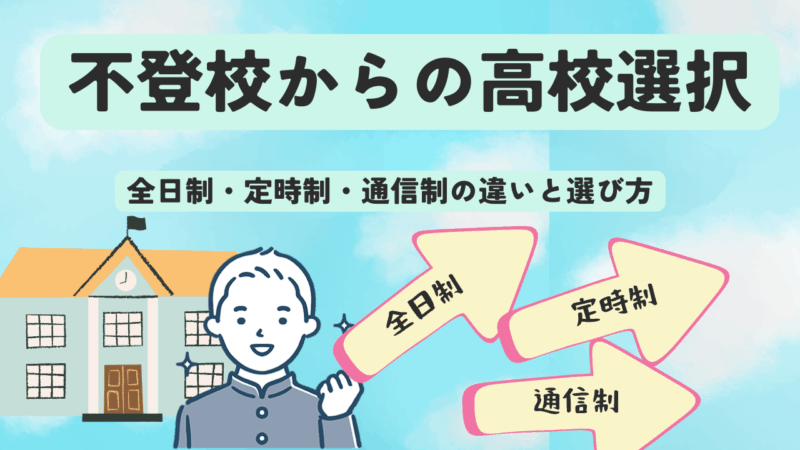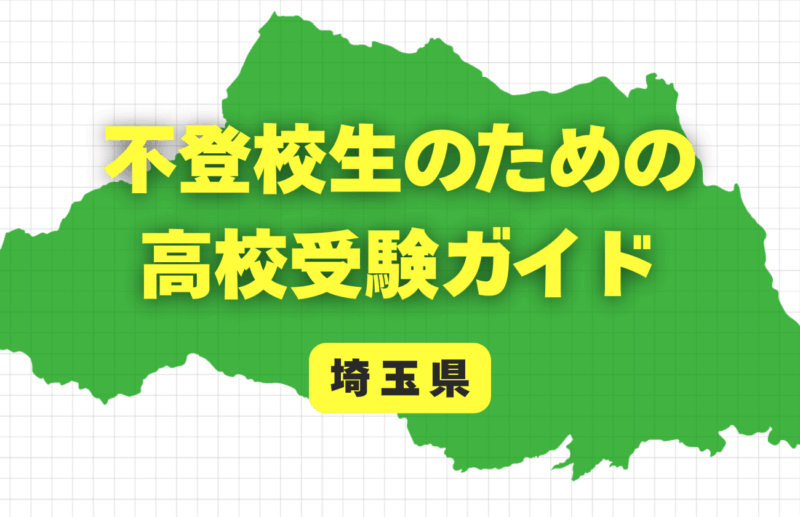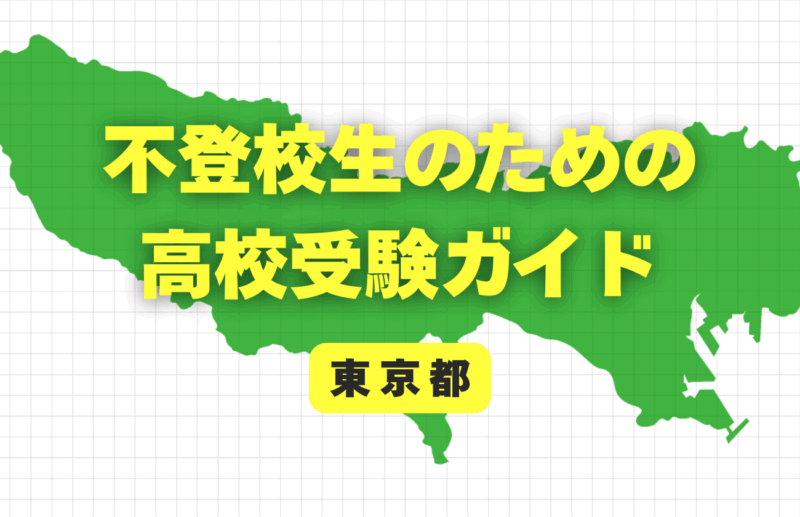不登校の不安に寄り添う|休む意味と親の役割



お子さんが学校に行けなくなったとき、多くの保護者の方がこうした不安を抱かれます。
しかし、不登校は特別なことではなく、子どもが自分を守るためにとる自然な反応でもあります。
本記事では、REO代表の阿部の著作 『不登校は天才の卵』 の内容をもとに、保護者の皆さまに安心していただけるよう 「休むことの大切さ」と「親ができる支え方」 をお伝えします。
少子化で集中する親の期待
かつては4〜5人きょうだいがいる家庭も多く、それぞれの子どもが得意分野を担っていました。
ところが現代では子どもの数が少なく、親の期待が一人に集中してしまいがちです。
「勉強も運動も、全部できるようになってほしい」という気持ちは自然なことですが、その期待が大きな重荷となることもあります。
一人で抱え込む子どものストレス
きょうだいがいれば愚痴を言い合ったり、近所づきあいがあれば気分転換ができたりした時代もありました。
しかし今は一人っ子や孤立しやすい環境も増え、子どもが安心して弱音を吐ける場が少なくなっています。
その結果、「期待に応えなければ」という気持ちが強まり、子ども自身を追い込んでしまうことがあります。
無理に学校へ行かせることの危険性
小さなつまずき――テストの失敗やケガなどが、大きな挫折感となって不登校につながることがあります。
「とにかく学校に戻さなければ」という思いから無理に登校させようとすると、かえって子どもを追い詰めてしまうことも。
繊細で感受性の豊かな子ほど、学校という競争的な環境で心をすり減らしてしまいやすいのです。
心配になるのは当然のことですが、子どもが休むことを受け止めることが大きな安心になります。

自治体によって運用は異なりますが、興味のある方はこちらの記事も参考にしてみてください。
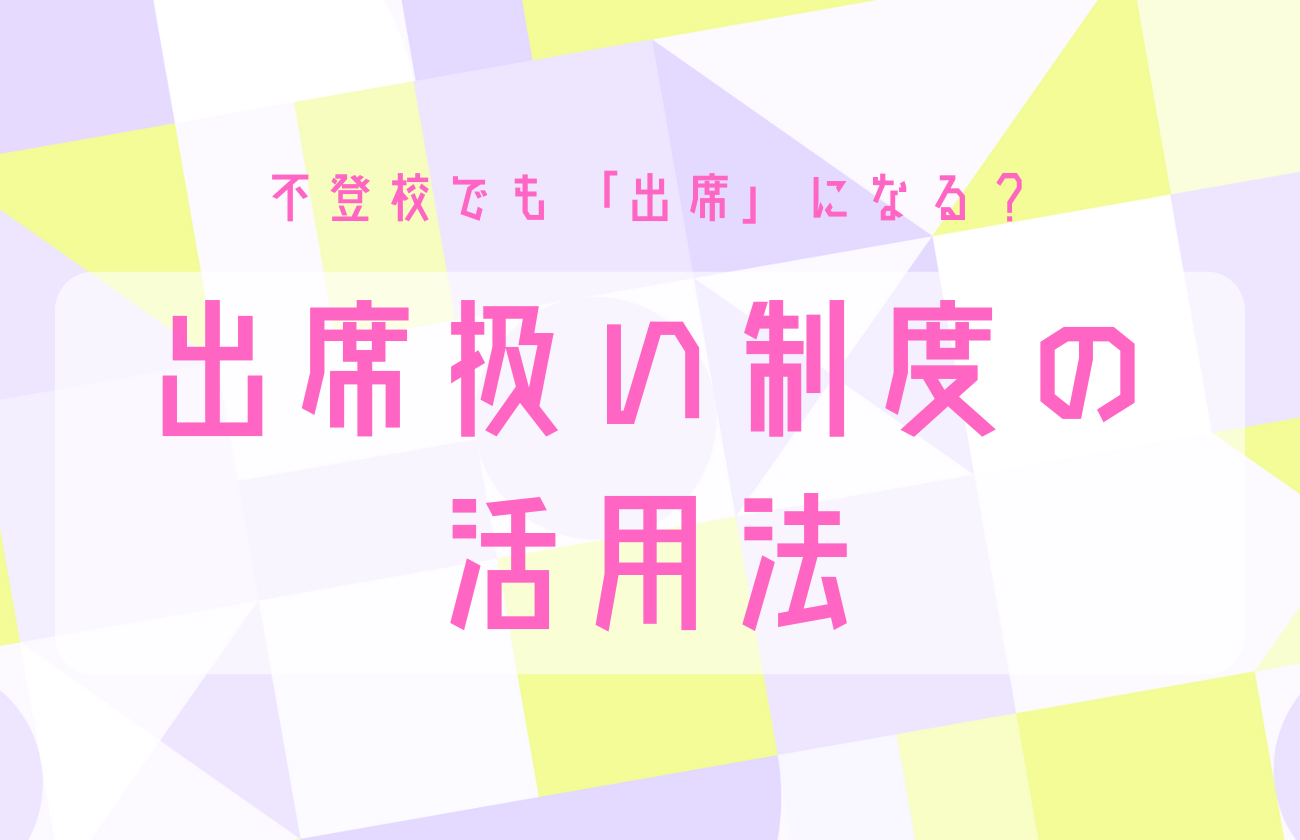
休むことは将来への準備になる

このような不安を感じる方も多いでしょう。
ですが、子どもは十分に休んで気持ちが落ち着くと、自然と自分の興味や学びたいことに目を向け始めます。
そのときに塾やフリースクールなど、安心して学べる場を整えてあげることが保護者の大切な役割です。

そう信じて待つことが、子どもにとって何よりの支えになります。
不登校の子どもたちが安心して学べる場として、各自治体が教育支援センターを設置しています。
教育支援センターについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
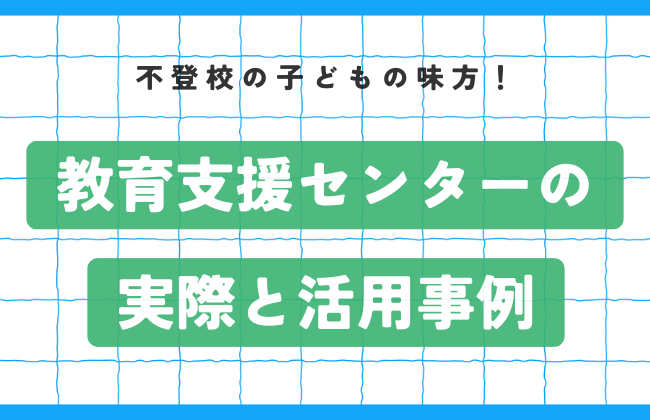
大人になってからの挫折よりも、子どものうちに休む方が良い
大人になってから「心が折れて動けなくなる」ケースの背景には、子ども時代に無理を続けてきた経験があるとも言われます。
だからこそ、子どものうちに休むことは将来への準備。

このように思えることが、長い人生を見据えたときにプラスになるのです。
まとめ|不安な気持ちを一人で抱え込まないで
お子さんの不登校は、親御さんにとっても大きな心配ごとです。
しかし 「学校に行かない=未来が閉ざされる」わけでは決してありません。
休むことを肯定し、再び学びたいと思ったときに道を整えてあげることこそ、保護者にできる最大の支援です。
どうか不安な気持ちを一人で抱え込まず、支援や情報を頼りながら一緒に次の一歩を考えていきましょう。
興味のある方は、こちらの保護者さまのインタビュー記事も参考にしてみてください。

困ったときは、ひとりで抱え込まないで
保護者さまだけで、不登校のお子さまを見守っていくには不安がつきものです。
REOでは、不登校のお子さまの状況や保護者さまが感じているご不安についてもご相談いただけます。
お気軽に下記のお問い合わせフォームや公式LINEよりご連絡ください。